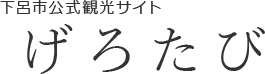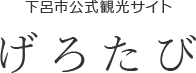本文
Moriminashi Hachiman Shrine(森水無八幡神社)
Moriminashi Hachiman Shrine is believed to have been founded during the reign of Emperor Nintoku in the fourth century CE. It enshrines Hachiman, a deity of archery and war. The shrine has several cultural treasures including a set of carved wood statuettes from the twelfth century. Numerous old-growth cedars grow on the grounds as symbols of the shrine’s long history.
Cultural traditions and treasures
The shrine is the main venue of the Tanokami Festival, an annual citywide celebration of thanks to the deities of the fields (tanokami). Every February 14, dancers, devotees, and spectators gather at the shrine to pay homage to the traditions of Gero’s agricultural past through dances and rituals.
One of the most treasured possessions held by the shrine is a set of wooden figurines that were carved by artisans from Hida Province (present-day Gifu Prefecture) in the twelfth century. These ten statuettes depict various deities and range from 30 to 60 centimeters in height. They are only displayed during festivals and on New Year’s Eve. The statuettes are designated an Important Cultural Property.
A mikoshi, or sacred palanquin used for Shinto festivals, is stored near the main hall of the shrine. The mikoshi was transported from Kyoto during the Edo period (1603–1867). It weighs around 600 kilograms, and 16 people are needed to carry it.
Near the main hall is a smaller shrine dedicated to Konpira Gongen, the deity of merchant sailors. This shrine is constructed in the azekura architectural style and is said to be modeled on the Shosoin Repository in Nara. Azekura is a traditional Japanese construction style characterized by chamfered logs stacked log-cabin style to form walls. In this method of construction, the wood expands and contracts in response to humidity, helping to better preserve the building’s contents.
Cedar trees past and present
A pair of meoto sugi, or “husband and wife” cedar trees, once stood on the shrine grounds, but only one of the trees remains. It has a 6.34-meter circumference and is believed to be several hundred years old.
The shrine once had another famous cedar tree that was more than 2,000 years old. This ancient cedar measured 13 meters in circumference and was considered one of the six sights of Gero that inspired the name of Mutsumi Bridge (literally “six-view bridge”) to the south. Unfortunately, the tree was partially destroyed by a fire in 1952 and eventually toppled in 1990. A young tree was planted in its stead, and a plaque memorializes the original cedar.
【日本語訳】
森水無八幡神社は西暦 4 世紀の仁徳天皇の時代に創建されたとされています。
この神社は弓と戦いの神である八幡神を祀っています。
この神社は12世紀の木の彫像一式などいくつかの文化財を所有しています。
境内には数多くの古杉が生い茂っており、この神社の長い歴史を象徴しています。
文化的伝統と文化財
この神社は田んぼの神様(田の神)感謝する毎年恒例の市全体で行われる田の神祭りのメインの場所です。
毎年 2 月 14 日には踊りや儀式を通して下呂の農業の伝統に敬意を表すためにこの神社に踊り子、信者、観客が集まります。
神社所有の最も貴重な所有物の 1 つは12世紀 に飛騨国(現在の岐阜県)の職人によって彫られた木像群です。
これら高さは 30-60 センチメートルの 10 体の小像にはさまざまな神が描かれています。
これらは祭りの期間と大晦日にのみ展示されます。
これらの小像は重要文化財に指定されています。
神社本殿の近くには神道の祭りで使用される神聖な輿、神輿が保管されています。
この神輿は江戸時代(1603年-1867年)に京都から運ばれたものです。
重さは約600kgあり、運ぶには16人が必要です。
本殿の近くには商船乗りの神様である金毘羅権現を祀る祠があります。
この神社は校倉造りで建てられており、奈良の正倉院をモデルにしたと言われています。
校倉は面取りした丸太を丸太小屋スタイルで積み上げて壁を形成する日本の伝統的な建築様式です。
この建築法では湿度に応じて木が膨張・収縮するため、建物内のものをより良い状態で保管する一助になります。
杉の今昔
かつて境内には夫婦杉がありましたが、そのうちの一本のみが残っています。
周囲は6.34メートルで、樹齢は数百年と考えられています。
神社には昔、樹齢二千年を超えるもう一本の有名な杉の木がありました。
この古代の杉は周囲13メートルあり、南にある六ツ見橋(文字通り「六景の橋」)の名前の由来となった下呂六景の一つと考えられていました。
残念ながらこの木は 1952 年の火災で部分的に焼失し、最終的には 1990 年に倒壊しました。
代わりに若い木が植えられ、元の杉を記念する銘板が建てられています。