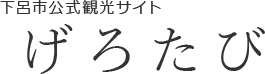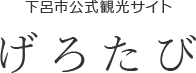本文
Kanayama Megaliths(金山巨石群)
Large, curiously shaped boulders sit atop a hill in the quiet forests of Gero’s Kanayama district, their muted appearance belying an extraordinary function. The Kanayama Megaliths are a sophisticated astronomical calendar and have been dubbed “Japan’s Stonehenge.” Arrowheads, earthenware, and other relics excavated in the vicinity date back approximately 8,000 years to the hunter-gatherer Jomon period (14,500–900 BCE) of prehistoric Japan.
The area is officially known as the Iwaya Iwakage Site and was designated a Site of Historical Importance by Gifu Prefecture in 1973. Independent researchers discovered the time-keeping properties of the boulders in recent decades. In 1997, an artist named Kobayashi Yoshiki found markings on one of the stones that he believed to be man-made. Kobayashi commenced an investigation of the area with fellow researcher Tokuda Shiho, and together, they compiled a wealth of information about the site. They eventually formed an organization called the Kanayama Megaliths Research Center.
The megaliths are positioned in three clusters. Kobayashi and Tokuda found that the edges of certain stones align perfectly with the position of the rising and setting sun during the equinox and solstice. Their placements imply a precise knowledge of astronomy and suggest that the stones were used as a solar calendar.
Additional discoveries suggest that the megaliths not only track the solar year, but also account for the deviation that is resolved via the leap year in the Gregorian calendar. The researchers came to this conclusion through careful observation of the angle of the sun and the shifting position of the sunbeam that enters an open-air chamber created by the positioning of the stones. By measurements calculated across a span of centuries, the time-keeping system of the Kanayama Megaliths is more accurate than that of the Gregorian calendar.
In addition to the solar calendar function, certain boulders of the Kanayama Megaliths are believed to indicate the North Star and the Big Dipper. Signboards around the site introduce the megaliths and the discoveries made to date through diagrams, images, and written explanations. Guided tours are available through the Kanayama Megaliths Research Center.
【日本語訳】
下呂市金山地区の静かな森の中の丘の上に面白い形の大きな岩々が鎮座しており、その落ち着いた外観とは裏腹に特別な役割を果たしています。
金山巨石群は洗練された天文暦であり、「日本のストーンヘンジ」とも呼ばれています。
付近で発掘された矢じり、土器、その他の遺物は、約 8,000 年前の先史時代の日本の狩猟採集縄文時代 (紀元前 14,500年-900 年) のものと推定されています。
この地域は正式には岩屋岩蔭遺跡として知られ、1973 年に岐阜県の指定史跡に指定されました。
独立した研究者らはここ数十年で岩が時を刻む性質を発見しました。
1997年、小林由来という画家が石の一つに人工のものと思われる模様を見つけました。
小林氏は研究員仲間の徳田紫穂氏とともにこの地域の調査を開始し、共同でこの遺跡に関する豊富な情報をまとめました。
彼らは最終的に「金山巨石群リサーチセンター」という組織を設立しました。
巨石は 3 つのかたまりに分かれて配置されています。
小林氏と徳田氏は特定の石の端が春分・秋分と夏至・冬至の日の出と日の入りの位置に完全に一致していることを発見しました。
それらの配置は天文学の正確な知識を暗示しており、石が太陽暦として使用されたことを示唆しています。
さらなる発見は、巨石群が太陽年を正確に追従するだけでなく、グレゴリオ暦の閏年によって解決されるずれの原因についても示唆していることです。
研究者らは太陽の角度と石の配置によって作られた屋外の空間に入る太陽光線の位置の変化を注意深く観察することによってこの結論に達しました。
何世紀にもわたって計算された測定結果よると、金山巨石群の計時システムはグレゴリオ暦よりも正確です。
太陽暦の機能に加えて、金山巨石群の一部の岩は北極星と北斗七星を示していると考えられています。
遺跡の周囲の看板では巨石群とこれまでの発見を図、画像、解説文で紹介しています。
金山巨石群リサーチセンターではガイド付きツアーを利用することができます。