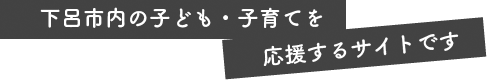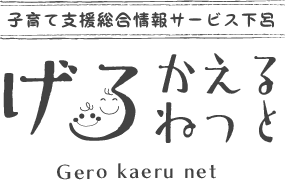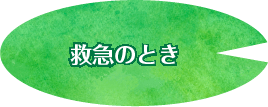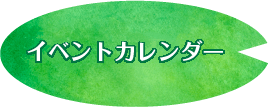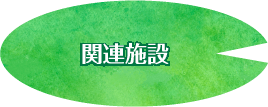本文
児童扶養手当
児童扶養手当制度のご案内
児童扶養手当とは
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当を受けることができる方
下呂市に住民登録があり、18歳までの児童を監護している母(父)、または父母に代わってその児童を監護(養育)している方が手当を受けることができます。
児童が心身に中度以上の障害がある場合は、20歳になるまで手当を受けることができます。
「監護」とは、保護者として児童の生活の面倒を見ることをいいます。
手当の対象となる児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に一定の障がいのある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄(監護義務を放棄)している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しない状態で生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
(注)児童とは・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者。
支給対象とならない場合
- 日本国内に住所がないとき
- 児童が、児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 児童が、父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいの場合を除く)
(注)事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます。事実婚は、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問や生活費の援助がある場合には、同居していなくても事実婚は成立します。
所得による支給制限
この手当には、所得による支給制限があります。
受給者本人または配偶者および扶養義務者の所得額により、手当額の一部または全部が支給停止となります。
また、公的年金給付・遺族補償等の給付額により、手当の一部または全部が支給停止となります。
|
扶養親族 等の数 |
受給者資格者本人 |
孤児等の養育者 配偶者/扶養義務者 |
||||||
| 全部支給 | 一部支給 | |||||||
| 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | |||
|
0人 |
1,420,000円 | 690,000円 | 3,343,000円 | 2,080,000円 | 3,725,000円 | 2,360,000円 | ||
| 1人 | 1,900,000円 | 1,070,000円 | 3,850,000円 | 2,460,000円 | 4,200,000円 | 2,740,000円 | ||
| 2人 | 2,443,000円 | 1,450,000円 | 4,325,000円 | 2,840,000円 | 4,675,000円 | 3,120,000円 | ||
| 3人 | 2,986,000円 | 1,830,000円 | 4,800,000円 | 3,220,000円 | 5,150,000円 | 3,500,000円 | ||
| 4人 | 3,529,000円 | 2,210,000円 | 5,275,000円 | 3,600,000円 | 5,625,000円 | 3,880,000円 | ||
| 5人 | 4,013,000円 | 2,590,000円 | 5,750,000円 | 3,980,000円 | 6,100,000円 | 4,260,000円 | ||
※収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額
次の式に当てはめて計算します。
【所得限度額と比較するための所得金額】=【所得額(注意1)+養育費(8割)】-【控除額(注意2)】-【児童扶養手当法施行令に定める控除額(8万円)】
(注意1) 所得額は、下記の所得額の合計です。
総所得金額(注意3)、非課税公的年金等(障害年金、遺族年金等)、退職所得金額、山林所得金額、土地等にかかる事業所所得等の金額、長期譲渡所得金額
短期譲渡所得金額、先物取引にかかる雑所得、条約適用利子等の金額、条約適用配当等の金額
(注意2) 控除額は、下記の控除額の合計です。
(給与所得・年金所得のある方)給与・年金所得控除(10万円。未満の方はその額)
雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額、障害者控除(普通27万円/人)(特別40万円/人)、寡婦・ひとり親控除(注意)受給者が父または母以外の場合(寡婦27万円/人)(ひとり親35万円/人)、勤労学生控除(27万円)、譲渡所得控除額
(注意3) 総所得とは、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額です。
支給される手当額について
| 対象児童数 | 全部支給 月額 |
一部支給 月額 所得に応じて支給額が決定されます |
|---|---|---|
| 1人目 | 45,500円 |
45,490円から10,740円 |
| 2人目以降 | 10,750円を加算 |
10,740円から5,380円を加算 |
| 対象児童数 | 全部支給 月額 |
一部支給 月額 所得に応じて支給額が決定されます |
|---|---|---|
| 1人目 | 46,690円 |
46,680円から11,010円 |
| 2人目以降 | 11,030円を加算 |
11,020円から5,520円を加算 |
(注)児童扶養手当の受給期間が5年(または支給事由発生から7年)を超える場合には政令の定めにより、就業しているまたは求職活動等の自立を図るための活動をしているなどの該当事由にあたらない方は、これまでの支給額の2分の1に減額となります。
手当の支払
1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、それぞれの支払月の前月までの2か月分が、届出された口座へ振り込まれます。
振込の日は各月11日ですが、11日が休日にあたる場合は、順次繰り上がっての支払いになります。
認定請求をした月の翌月分から支給の対象となります。
必要な手続きについて
認定請求(申請)手続き
手当を受けるためには、認定請求(申請)の手続きが必要です。
手当を受ける方の支給該当要件、世帯の状況などによって、申請手続きに必要な書類が異なる場合があります。
なお、下呂市に転入される方で、転入前の市町村で児童扶養手当の認定があった方は、児童扶養手当転入届を提出してください。
認定請求(申請)に必要な書類
- 児童扶養手当認定請求書(窓口に備えてあります)
- 請求者および対象児童の戸籍謄本
※離婚を理由に申請する方は、離婚日等が記載されている、交付後1か月以内のもの。(請求者と対象児童が別戸籍の場合は、各1通必要になります。) - 請求者と児童、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
- 所得課税証明書
※マイナンバー(個人番号)を利用した情報提供ネットワークの運用開始により、提出が省略できるようになりました。 - 請求者名義の金融機関の預金通帳
- 請求者の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳など)
- 請求者と児童の保険証情報がわかるもの「健康保険被保険者証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」のいずれか(これらは、ひとり親医療受給者証交付申請を行う際必要となります)
(注)上記以外に必要となる書類は申請時にご案内します。
届け出の内容などに変更があったとき
受給資格者が、次のいずれかに該当する場合は、すみやかに必要な手続き、または届け出をしてください。
手続きや届け出が遅れると、手当が受けられなくなったり、支給を受けた手当を返還していただく場合があります。
- 対象児童が増えたとき
- 対象児童が減ったとき
- 住所が変わるとき(市内での転居、市外へ転出される場合)、氏名が変わるとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居することとなり、支給区分が変更するとき
- 受給者やその配偶者、対象児童が、公的年金や遺族補償等を受けるようになった、またはお子さんが公的年金の加算対象となったとき
- 受給者または、ご家族の方が所得申告の内容を修正したとき
- 手当証書を失くしたとき
- 手当証書を破損したり、汚してしまったとき
- 氏名・住所・支払金融機関が変わったとき
資格喪失届の提出
次のような場合は、手当てを受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受けた場合、資格がなくなった月の翌月分からの手当をさかのぼって全額返還していただくことになります。
- 受給資格者が、婚姻したとき(事実婚の状態になったとき)
- 受給資格者、または対象児童が死亡したとき
- 対象児童が、児童福祉施設に入所、または里親に委託されたとき
- 対象児童が転出などにより、監護または養育されなくなったとき
- 遺棄した父または母から連絡があったとき
- 父または母が拘禁解除されたとき
(注)児童扶養手当法第35条には罰則規定があり、「偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。支給要件に変更があった場合、必ず届出をしてください。
現況届について
受給資格者(所得超過による支給停止の方を含む)は、毎年8月に現況届の提出が必要です。7月末にご案内の文書を郵送します。
現況届は、引き続き手当を受ける要件を満たしているか確認し、11月分以降の手当の支給について審査するためのものです。
提出がない場合は11月以降分の手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出してください。
また現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童扶養手当の支給を受ける権利がなくなります。
所得が制限限度額を下回る見込みがなく、手当が今後も全部停止となる見込みの方などで、現況届の提出を希望されない方は、「辞退届」を提出できます。
「辞退届」を提出されると、児童扶養手当の受給資格は「喪失」となり、「資格喪失通知書」が送付されます。
手当の一部支給停止について
児童扶養手当の受給開始から「5年を経過する等の要件」に該当した場合、受給資格者やその子ども等の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない方については、児童扶養手当の支給額の2分の1を支給停止とすることになっています。
「5年を経過する等の要件」とは次のいずれか早いほうを経過する場合をいいます
- 支給開始月の初日から起算して5年
- 手当の支給要件(離婚・父の死亡等)に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
※父たる受給者が平成22年8月1日において現に手当の支給要件に該当している場合等については、平成22年8月1日が起算日となります。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとなります。
一部支給停止の適用除外事由について
上記に該当される方のうち、次の「一部支給停止適用除外事由」に該当する場合は、『一部支給停止適用除外事由届出書』と『必要書類』を提出することにより、従来どおり同額の手当を受給することができます。
対象の方には毎年6月下旬までに案内通知を郵送しますので、その年の現況届とあわせて提出してください。なお、対象となった年度以降は現況届を提出する際に届出書の提出が必要となります。
| 適用除外事由 | 必要書類の例 |
|---|---|
|
就業している場合 |
保険証情報がわかるもの「健康保険被保険者証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」のいずれか。 または「雇用証明書」または「自営業従事申告書」等 |
|
求職活動等の自立を図るための活動をしている場合 |
「求職活動等申告書」「求職活動支援機関等利用証明書」「採用選考証明書」等 |
|
身体上または精神上の障害がある場合 |
障害年金等年金証書または身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し |
|
負傷または疾病等により就業することが困難である場合 |
診断書または特定疾患医療受給者証、特定疾病療養受領証の写し |
|
児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合 |
児童または親族の方の介護を行わなければならない事情を確認できる書類 |
児童扶養手当に関するよくある質問
児童扶養手当に関するよくある質問をまとめました。
お問合せ窓口
新規認定のご相談は市民サービス課、その他各種届出は最寄りの振興事務所でお手続きできます。
市民サービス課 0576-24-2222 下呂市森960番地
萩原振興事務所 0576-52-2000 下呂市萩原町萩原1166番地8 星雲会館内
小坂振興事務所 0576-62-3111 下呂市小坂町小坂町815番地5
金山振興事務所 0576-32-2201 下呂市金山町大船渡600番地8
馬瀬振興事務所 0576-47-2111 下呂市馬瀬名丸406番地