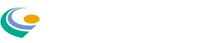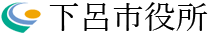本文
後期高齢者医療保険料
令和7年度保険料の算定方法
後期高齢者医療制度では、被保険者の方全員に保険料を納めていただきます。
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、個人単位で計算されます。
令和7年度の保険料 =「均等割額」(49,412円)+「所得割額」{被保険者の所得×所得割率(9.56%)}
- 保険料の賦課限度額は80万円です。
- 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。
- 被保険者の所得=総所得金額等-43万円(基礎控除額)
(注)合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額が少なくなります。
所得の低い方の軽減について
均等割額の軽減
「被保険者本人」「同一世帯のその他の被保険者」「被保険者でない世帯主」の所得の合計が一定以下の場合、保険料の均等割額が下記の基準により、7割・5割・2割軽減されます。
| 軽減割合 |
所得要件 { }内は給与所得者等が2人以上の場合に計算します。 |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等※の数-1)} を超えない世帯 |
| 5割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等※の数-1)}+(29万5千円×被保険者数) を超えない世帯 |
| 2割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等※の数-1)}+(54万5千円×被保険者数) を超えない世帯 |
※給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える方、または公的年金等に係る所得がある方(公的年金の収入が65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)です。
均等割額軽減判定時の総所得金額は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は、年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。 軽減判定日は、毎年4月1日または資格を取得した日となります。
被用者保険の被扶養者であったことによる保険料の軽減
制度加入前日まで被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、後期高齢者医療保険加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方は、いずれか大きい方の額が軽減されます。
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、納付書や口座振替でお支払いいただく「普通徴収」があります。
特別徴収(年金天引き)
年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。
(仮徴収)4月【1期】、6月【2期】、8月【3期】※年間保険料が確定していないため、前年度の保険料額を基に仮計算した保険料額を納めていただきます。
(本徴収)10月【4期】、12月【5期】、2月【6期】※確定した年間保険料額から、仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて納めていただきます。
【75歳となる方の特別徴収(年金天引き)が始まる月について】
- 1月1日~5月31日に75歳となる方・・・10月開始
- 6月1日~10月2日に75歳となる方・・・翌年の4月開始(前々年所得での仮徴収)
- 10月3日~12月31日に75歳となる方・・・翌年の10月開始
年金天引きになるまでは納付書または、口座振替での納付となるため、納め忘れのない「口座振替」をおすすめします。
普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)
年金からのお支払いとならない方は、市から送付される納付書や、口座振替によりお支払いいただきます。
【次に該当する方は普通徴収となります】
- 特別徴収の要件に該当しない方
- 後期高齢者医療制度に加入したばかりの方
- 他市町村から引っ越したばかりの方