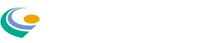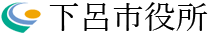本文
9月定例会一般質問の内容(質問要旨と質問項目)
本定例会では、一般質問で13人の議員が市政について質問を行います。
一般質問
9月13日(金曜日)午前9時30分開会
|
【予定時間】 発言議員 |
質問要旨 | 質問項目 |
|
【午前9時30分から】 桂川いずみ |
1.今後も続くだろう酷暑対策について 下呂市でも猛暑日「熱中症警戒アラート」暑さへの「気付き」を呼びかけるための広報無線が頻繁に流れた。7月8月には気温が35℃を超える猛暑日が記録された。本来朝晩の気温の変化や避暑地でもあるはずのこの地域でも猛暑が続く事は健康被害や、活動の制限、仕事の効率の低下、農作物被害につながる危険性を踏まえ市の温暖化対策についての考えを問う。 |
(1)市内におけるクーリングシェルターの活用状況は。今後の対策の拡大等の検討は必要と感じるが、どのように考えているか。 (2)地球温暖化に伴い、今後も続くだろう酷暑を見据えたまちづくり、環境整備は必策と感じるが、市の対策や方向性はどのような考えか。 (3)公園等人が集まる場所の持続可能な地中熱冷却や水力の活用などの整備は不可欠と思うが、どのような対策を考えているか。 |
|
2.身を守るための様々な支援の見直しについて 今後毎年、酷暑が続くと推測されるが、高齢者や子ども、屋外作業従事者が暑さから身を守るために適切な対策を取る事が必策であると思う 。市民の安全を守る事が優先課題と感じるが、当局の考えを伺う 。 |
(1)施設や独居・高齢者世帯への支援、声掛けはさせていると思うが、サポートしてくださる方の人員は不足していないか。 (2)地域ボランティアの方も高齢化していると思うが、指導体制の見直しやボランティアの方々への支援はどの様に考えているか。 (3)災害時等でいち早く活躍していただける現場作業員の方々への身を守る為の装備備品配布などに公助の支援策を検討できないか。 |
|
|
3.物価高騰を緩和する下呂市の支援、取り組みについて 今年の気候の特徴である酷暑や水害に伴い、家庭での水道光熱費の増加や、様々な物価高騰の要因が、家計の圧迫に拍車がかかっている。市民一人一人が満足な生活を送ることを目指し、市内全体が持続可能な社会的、経済的、環境的に発展する為に、当局の将来的な支援を具体的に問う。 |
(1)非課税世帯等からの物価高騰対応重点給付金の申請はスムーズに進んでいるか。 (2)地産地消を強化する事で物流コストを抑えられる身近な「道の駅」「販売所」「朝市」などの活用は不可欠かと思うが、この状況をどのように考えているか。 (3)市民生活アンケート結果はまとめられているが、生活満足感や地域愛着などの状況を市はどう捉えているか。 |
|
|
【午前10時10分から】 森 哲士 |
1.市有林の管理と森林整備について 市有林の管理と施業の実施状況について、及び国が進める森林経営管理法に基づく管理体制の現状と今後の方針について問う。 |
(1)市有林の管理は十分に引き継がれているか。 (2)市有林の施業は適正に実施されているか。 (3)主伐・再造林は実施されているか。 (4)国全体では人工林の64%が植栽から50年を経過した成熟期となっているようだが、市有林の状況はどうか。 (5)森林経営管理法に基づく市の取組みの状況は。 |
|
2.JA旧下呂支店の用地の活用について 現在、駐車場増設として土地活用が計画されているが、下呂庁舎の市民窓口は狭く、各部署が分散している。また、会議室が不足しており、住民相談など十分なプライバシーを確保することが困難である。現庁舎が抱える課題を解決し、市民にとってより良い環境を整えるためにも、市が用地取得後の活用は何を想定しているのか。 |
(1)現在、下呂庁舎は手狭であり、バリアフリー化にもなっていない。また、市民はもちろん職員も不便を感じている。市民にとってより良い環境にするためには、庁舎の増築が有効と考えるが、JA旧下呂支店の用地の活用について問う。 | |
|
【午前11時00分から】 鷲見昌己 |
1.地元で学び、働き、暮らすことができる選択肢拡大について 下呂市では、高校や大学への進学や、就職を機に、多くの若者が市外へ転出しているのが現状である。このような社会減を減少させることが喫緊の課題と考える。地域の若者が、地元で学び、働き、暮らすことができる選択肢拡大につながる施策について問う。 |
(1)高校生の通学費助成制度拡充について。 (2)通信制大学と連携協定し、下呂サテライトキャンパスを設置し、地元での学びの場確保に向けた取り組みについて。 (3)雇用した従業員を専門教育のため、教育機関(高校、大学、専門学校)に送り出し、即戦力となる人材を確保する取り組みに対する支援について。 |
|
2.市道の環境美化、道路維持修繕、道路情報提供等地域住民によるボランティア活動への支援について 県道の場合、地域住民・団体や企業の自発的なボランティア活動により、定期的に清掃・除草や除雪などの維持管理を行う「ぎふ・ロード・プレーヤー」事業により、一定の支援がされている。集落間(住宅が隣接しない道路部分)を結ぶ市道でも同様な活動が行われているが、支援の現状と今後の対応について問う。 |
(1)市道の維持管理に対する現行の支援体制について。 (2)集落間を結ぶ市道に対する課題について。 (3)地域住民やボランティア団体が行う市道の維持管理活動支援制度構築について。 |
|
|
【午前11時40分から】 加藤久人 |
1.耐震化されていない指定避難所について 災害時の緊急避難場所として、市内に113か所が指定されており、その内53か所が指定避難所に指定されている。53か所の内には、各地域にある公民館も指定されているが、内5か所の公民館は耐震強化されていない施設である。 耐震強化されていない施設を指定避難所とすることに対する市民の不安があるが、その点についての市当局の考えを問う。 |
(1)耐震強化されていない公民館等の施設を指定避難所とするのはいかがかと思うが、市の見解を問う。 |
|
2.廃校となった旧小学校の活用について 金山町の東・菅田地区にある両公民館とも老朽化が酷い状況であるにも関わらず、日常の会議等で使用されている。しかも約1km以内には、耐震化されている旧小学校の校舎があり、そちらを使用しないことに対して市民の疑問が上がっているが、その点についての市当局の考えを問う。 |
(1)選挙や地区の会議など耐震の無い公民館を使用するより、耐震強化された旧小学校校舎を使用する方が危険リスクは下げられると思うが市の見解を問う。 (2)指定避難所として体育館が指定されているが、各教室の方が細かく仕切られており、プライバシーの面からも適していると思えるが市の見解を問う。 (3)旧小学校の利用について、今後の方針を問う。 |
|
|
3.飛騨萩原駅、 飛騨金山駅の今後の活用について 飛騨萩原駅と飛騨金山駅は平成24 年 4 月より JRの無人化に伴い、住民の熱望により市からの活性化事業交付金を受け、萩原町観光協会と金山町商工会が簡易委託駅としての出札業務と観光情報の発信を行っている。 利用客が減少し増収が臨めない中において、 最低賃金の大幅な改正などにより経費は増額する一方であるが、 今後の方向性について市当局の考えを問う。 |
(1)最低賃金の大幅な改正に伴い、交付金の増額が無い限り、出札業務における営業時間又は日にちの短縮が余儀なくされることになるが、今後交付金の増額はあるのか市当局の考えを問う。 (2)両駅とも地域の観光の拠点として重要な位置を占めているが、今後の活用について市当局の考えを問う。 |
|
|
【午後1時30分から】 下平裕次郎 |
1.下呂市こども計画の策定について 少子化が顕著に進んでいる当市において、未来の宝物である子どもたちのために、この計画は非常に重要なものである。本計画の策定にあたり、その目指すものはなにか。 |
(1)本計画により目指すものは何か。 (2)市民の意見、特に今の子どもたちの意見が重要であると考えるが、どのように計画に反映していくのか。 (3)子どもに関わる担当課は複数にまたがるが、重要なことは横の繋がりであると考える。それらのことを計画に明記することが必要であると考えるがいかがか。 |
|
2.災害時に給食センターを防災拠点へ 大災害発生時などの非常時に全国的には備蓄する食料や調理器具を活用して炊き出しを行う給食センターが広がっている。災害への備えをさらに強化するためには、「食」を核とした取り組みが重要であると考えるが、当局の考えを問う 。 |
(1)今後市として、災害時に給食センターを炊き出しや備蓄などの防災拠点とする考えはあるのか。 (2)現在市内に備蓄してある非常食は何食分あるか。また主な非常食はどのようなものか。 (3)炊き出しを行うことができる施設はどれだけあるか。 またそれを運ぶ手段はどうするのか。 |
|
|
3.防災対策のソフト面強化について 防災訓練などのソフト面での防災対策は市民の防災意識を高め、災害時の備えとして非常に重要であるが、当局としての取り組みを問う。 |
(1)防災対策へのソフト面での当局の取り組みを問う。 (2)防災フェスが全国各地で盛んに行われ、子どもから大人まで楽しみながら防災について学ぶ企画があるが、当局で今後取り入れる考えはあるのか。 |
|
|
【午後2時10分から】 田中喜登 |
1.市の子育て支援策について 6月定例会の所信表明の中で市長は重要課題のまちづくりと人口減少対策を進めると述べられ、人口減少対策の核を成す一つとして、「出産・子育て・教育の充実」を挙げられている。昨年子育て応援ブックが刷新され配布されたが、市民の方々への周知徹底が不十分に感じる。今一度、市の福祉部、教育委員会で取組んでいる少子化対策について伺う。 |
(1)下呂市が取組んでいる少子化対策について、特徴的なものとして、どのようなものがあるのか。 (2)市長は6月定例会の一般質問の答弁の中でランドセルの無償配布や教材費への支援に触れられ、その後保護者アンケートも実施したと聞くが、その取り組みの進捗状況について伺う。 |
|
2.若者が帰って来やすい環境の整備について 1つ目の質問で触れた人口減少対策の核を成す2番目として、「労働力の確保と生活支援メニューの充実」が挙げられている。市では今年度の取組みとして、市内への就職者の奨励金やUターン奨励金等、様々な新規事業を展開し、労働力確保に取組んでいる。また今年3月の代表質問に対し、県の制度とリンクさせ、地元企業も組み込んだ新しい奨学金制度を計画しているとの答弁があった。これらのことについて2点伺う。 |
(1)現在までの市内への就職者の奨励金やUターン奨励金等新規事業の利用状況はどうなっているか。 (2)新しい奨学金制度の計画の進捗状況はどうなっているのか。 |
|
|
3.障がい者の就労支援と入居施設について 市内には現在9箇所の障がい者就労支援施設があるが、萩原以北は「ひだまりの家」のみであり、北部の方々(特に小坂方面)は利用しづらく、市民サービスの観点からするとバランスの取れた配置になっていない。また、市内には障がいのある若い世代が入居できる施設がないため、やむを得ず市外の施設にお世話になるケースもあると聞いている。このような障がい者とそのご家族を取り巻く環境の改善に向け2点伺う。 |
(1)萩原以北の現況について、市はどのように考えているのか。今後の展望は。 (2)ご家族亡き後の状況に対応していくためにも、障がいのある若い世代が入居できる施設が必要と考えるが、市の見解は。 |
|
|
【午後3時00分から】 中島ゆき子 |
1.令和5年度決算審査意見書について 下呂市監査委員から提出された令和5年度審査意見書では、3件の事項について指摘されている。その詳細について問う。 |
(1)令和4年8月におきた後期高齢者医療広域連合納付金の誤納について、何故このようなことがおきたのか。 1.毎月の納付金については、保険料を100万円台で支払うことはあったのか。 2.ダブルチェックをしていれば、金額を間違えることはなかったと考えるが、正しい手順を踏んでいたのか。 3.後期高齢者医療広域連合からの指摘により、納付不足分を令和5年6月に納付しているが、昨年の9月定例会の決算特別委員会では、このことが報告されていない。今年になってからの報告になった理由は。 (2)社会資本整備総合交付金を活用した住宅・建築物安全ストック形成事業の中のアスベスト含有調査事業について、令和6年5月10日付けで、岐阜県からの返還命令書により返還を求められているが、その手続きは。 1.アスベスト含有調査実施業者が事業を完了したのはいつか。 2.アスベスト含有調査事業の25万円を国に返納することになったが、手続きはいつ行うのか。 3.国の補助金を活用できなくなり、下呂市の一般財源から支出することになったが、その手続きの方法は。 4.市長がこの件を知ったのはいつか。どのような対応をするように指示を出したのか。 5.この件を議会へ報告していないが、監査委員の意見書が出るまで待っていたのか。 (3)下呂市ふるさとワーキングホリデー運営委託業務に係る支払いについて、算定誤りの支払金額の処理はどうなったか。 1.支払にあたり、どのようなチェックを行っているのか。 2.委託先との協議はどうなったか。 |
|
2.可燃ごみの出し方について 可燃ごみの出し方が、令和5年度からは指定ごみ袋から無料のシールを貼って出す方法に変わったが、財政の影響について問う。 |
(1)令和5年度決算書から見えてきた財政への負担と受益者負担について、市の考えは。 1.ごみ袋の販売による収入は、可燃ごみのごみ袋販売が全体の9割近くを占めていたが、令和5年度は令和4年度と比べてどれだけの減収となったか。また、無料券の印刷、配布などにより、増えた費用の金額は。 2.クリーンセンターの運営と施設の整備など、ごみの処理は市の財政に大きな負担となっている。ごみを多く出す人とそうでない人の受益者負担についてはどのように考えているのか。 |
9月17日(火曜日)午前9時30分開会
| 時間 | 発言議員 | 質問事項 |
|
【午前9時30分から】 高井範和 |
1.非常時の適切な情報発信と停電対応について 8月8日、南海トラフ地震臨時情報に関する防災行政無線、下呂市メール等による市民周知は1回のみで充分ではなく、市民が地震に警戒する中にもかかわらず、地震とは関係のない情報発信があった。また、現状、停電発生に関する情報は市民配信されていない。非常時等における適切な情報発信のあり方について、市の考えを問う。 |
(1)非常時における市民への適期適切な情報発信のため、頻度等の取り決めや事前に設定された通常情報の取り消しなど情報管理・統制の必要があるのではないか。 (2)停電発生状況の把握方法は。また、停電の規模、原因の如何を問わず、市民の不安感を払拭するためにも停電情報を発信すべきと考えるが、市の見解は。 |
|
2.災害時における自助・共助・公助と暴風対策について 発災後の初期対応には市民の自助・共助、行政による公助がバランスよく機能することが重要である。地域の実態に即した防災訓練・体制づくりについて市の考えを問う。また、近年暴風被害について懸念されるが、対策について市の考えを問う。 |
(1)各地区に対する備蓄品調査結果をどう捉えているか。また、現状の一時避難所・指定避難所の備蓄品・資機材では充分ではなく、今一度、個人・地区での備えの重要性を訴える必要があるのではないか。 (2)一時避難所の開設について、地区・防災士等の意識向上と手順書の策定指導、開設訓練が必要ではないか。 (3)暴風対策の指針策定、点検、対策に対する支援補助を考える必要があるのではないか。 |
|
|
3.森林の境界明確化と地籍調査について 森林環境譲与税を活用した間伐事業やCO2削減、治山治水などから森林に関する関心は高まっている。一方で森林所有者の高齢化や山に対する意識の希薄化が進み、境界の不明確な林地が多く、今後の森林整備事業推進に支障となるものと危惧されるが、森林の境界明確化に向けた市の考えを問う。 |
(1)各地区の森林造成組合に対して、境界の明確化に向け、主体的に取り組んでいただくよう働きかけを行い、市はその活動を支援していく仕組みを作り、推進したらどうかと考えるがいかがか。 (2)地籍調査の取り組み状況と今後の方針は。 |
|
|
【午前10時10分から】 大西尚子 |
1.HPVワクチンのキャッチアップ接種について 女性の多くが一生に一度は感染するといわれるHPVウイルス。感染を防ぎ、がんにならないためにも有効なHPVワクチンのキャッチアップ接種は今年度が最終年度で対象年齢の接種状況や救済措置について問う。 |
(1)下呂市キャッチアップ接種の認知度を高める取り組みと、対象年齢の何割の方がワクチン接種したのか。 (2)接種が来年度に持ち越しになる人がいる場合の救済措置は考えているか。 |
|
2.高校生インフルエンザ予防接種の公費負担について 高校生が人生を決める大切な時期。地域を支える若者を支援するため公費助成の対象年齢の拡大について問う。 |
(1)地域の将来を支える若者を支援するため公費助成の対象年齢の拡大は考えているか。 | |
|
3.市民の健康寿命を延ばす取り組みについて 市民一人一人の生活の質を維持し平均寿命と健康寿命を延伸させる取り組みや今後の促進方法について問う。 |
(1)下呂市では市民の健康寿命を延ばす健康課題の取り組みとその成果について問う。 (2)今後の市民への周知方法、参加の促進方法の考え方はいかに。 |
|
|
4.下呂市医療ビジョンについて 第三次下呂市医療ビジョンが策定された。下呂市の医療体制、医療を守る人材の確保、地域医療を守り育てる活動の三点。医療ビジョンの実現に向けて市の考え方について問う。 |
(1)救急外来を軽症で受診した件数と市民への啓発方法について問う。 (2)現在の救急体制についてどのように考えているか。 (3)市民が安心して診療できる体制をどのように考えているか。 |
|
|
【午前11時00分から】 尾里集務 |
1.有害鳥獣の取り扱いについて 全国的にも問題になっている熊の出没が下呂市でもおきている。現に6月には小坂町で熊に襲われ重傷を負われる事案が発生した。環境省では熊類を指定管理鳥獣に追加した。市は、現在下呂市猟友会会員に対する有害鳥獣の駆除を依頼しているが、くくり罠に錯誤で掛かった熊に関しても指定管理鳥獣の扱いに出来ないか。また、小動物に関しても、もう少し捕獲報奨金を増額することは出来ないか。 |
(1)猪、鹿と同様に熊がくくり罠に掛かった場合の捕獲報奨金を考えられないか。 (2)小動物の捕獲報奨金を増額することはできないか。 |
|
2.下呂市森林づくり基本計画について 市は森林づくり基本計画を策定した。下呂市の森林・林業・木材産業を取り巻く現状を見つめなおし、持続可能な森林づくりを進めているが、方向性は示されたのか。 |
(1)下呂市の森林・林業・木材産業の現状と課題は。 (2)観光立市下呂において観光地にふさわしい観光景観林の現状と課題は。 (3)森林・林業・木材産業の将来像の現状と課題は。 (4)森林境界明確化の現状と課題は。 |
|
|
【午前11時40分から】 田口琢弥 |
1.過去の質問事項における検証について 過去の一般質問で取り上げた数々の事業。今回は環境・下水道事業について、各事業の現状や進捗状況等の検証を問う 。 |
(1)浄郷苑内トイレ改修と水質検査の結果と対策について。 (2)モデル地区のカゴによる資源ごみ収集事業。現在の状況は。また、既にカゴによる収集をやめた地区もあり使用していたカゴの行方は。 (3)市にストックしてある以前使用していた市指定可燃物袋は。「能登半島地震」で被災され、使用要望があった自治体への配布状況は。 (4)現在、幸田浄化センターが耐震・機器類更新が行われている。今後の他地域における下水道施設の改修計画は。 (5)令和6年4月からライフライン確保・継続のために上水道の料金改定が行われた。上水道同様に下水道事業の確保・継続の為料金改定が行われると聞いているがそのスケジュールは。 (6)下水道事業継続のため特定地域は下水道から合併浄化槽への切り替えが行われている。現在までの切り替え件数と費用、今後の計画は。切り替える事により現在どの位の維持管理費等の削減になったのか。また、今後の維持管理費等の削減費用は。 |
|
2.宿泊税導入について 日本国内各地域でインバウンド対策や観光振興、持続可能な観光地継続のために導入・検討されている「宿泊税」。下呂市も来年度より導入が計画されている。「宿泊税」について問う。 |
(1)宿泊税とはどういった税金なのか。 (2)宿泊事業者との合意形成はなされたのか。例えば導入時期と宿泊料に応じた定額制か宿泊料に対しての税率なのか。 (3)「宿泊税」が導入されることにより年間どの位の税収が見込まれるのか。また、「宿泊税」の使途先は何を想定しているのか。 |
|
|
【午後1時30分から】 桂川融己 |
1.移住定住促進への具体的な取り組みについて 下呂市は最重要課題に「人口減少」を掲げ、その対策の一環として補助金制度を設け、移住定住・Uターンを推進している。一方で、「令和5年度の県外からの移住者数」において、飛騨地域全体が増加する中、下呂市は対前年12名減の30名。移住定住促進の取り組みに対する評価と、今後の取り組みについて当局の考えを問う。 |
(1)2040年の下呂市の移住定住・Uターン者割合はどれくらいの想定か。 (2)移住者数が減っている現状をどう捉えているか。各種支援策の成果と現状評価は。 (3)支援策を使うことなく移住してきた人の数、そのうち外国人の数は。 (4)移住候補者が下呂市への移住を思い留まる要因として目立つものは何があるか。 (5)施政方針で触れている「市が空き家を借り上げ、市営住宅として賃貸する新たな制度の創設」の進捗状況は。 |
|
2.南飛騨Art Discovery継続開催の検討状況について 大地の芸術祭「越後妻有アートトリエンナーレ」の主催地である十日町市の担当者も、当事業の総合ディレクター北川フラム氏も「3回やることが大切」と継続の意義を語る。継続開催に対する検討状況を含めた当局の考えを問う。 |
(1)継続開催の重要性について、どう考えているのか。 (2)継続開催すると仮定した場合、いつ頃からどのような準備が必要となるか。いつ頃、意思決定が必要となるか。 (3)仮に当該事業に関する基金を創設する場合、考えられる財源は。 |
|
|
3.下呂市職員の人材育成・ 確保への取り組みについて どんな組織も「人」が重要とされ、市役所も例外ではないが、地方公務員のなり手不足は全国的な課題となっている。下呂市のために働く職員が意欲高く、強みを発揮しながら働ける環境を整備することは市政運営にとっても、人材確保の面でも重要である。中長期的視点に立った人材育成・確保について当局の考えを問う。 |
(1)新卒採用、中途採用、早期退職の状況とその課題は。 (2)職員の研修受講など人材育成への取り組み状況をどう捉えているか。 (3)なり手不足の現状をどう捉え、どのような対策をしてきたか。今後の対策の検討状況は。 (4)人材育成・確保基本方針の策定に向けた動きはあるか。 (5)若手職員によるプロジェクトや、外部との共同プロジェクトなど、若手も挑戦し活躍できる組織風土をつくるような取り組みをすべきではないか。 |
|
|
【午後2時10分から】 今井政良 |
1.酷暑による熱中症とスポーツ練習、大会の見直しについて 酷暑で熱中症による後遺症が必要以上に心配される中で、中学生の部活動、小中学生のスポーツクラブの練習及び夏休み期間中の各大会開催について見直しの検討が必要と思われる。教育面から捉えた考えを問う。 |
(1)酷暑時における小中学生の部活動とスポーツクラブの練習及び大会開催時の条件、対応制限が必要と思われるが、どのような対応をされているか。 (2)酷暑期間中に開催される大会の開催変更は出来ないか。 |
|
2.新設された人口減少、少子化支援対策事業の成果、実績について 少子高齢化が進む下呂市において新設された人口減少、少子化対策支援事業として、移住、定住、新規雇用者、結婚、出産、第2子、第3子、第4子以降の支援事業の成果を検証する必要がある。今後も新たなる支援事業を拡大し、対応しなければならない。子育て支援で新たな教育面関係での支援策の考えを問う。 |
(1)新設された人口減少、少子化対策支援事業をどのように評価されているか。 (2)それぞれの支援事業の実績は。 (3)子育て支援において教育面での新たな支援策の考えは。 |
|
|
3.避難所の整備について 近年の異常気象を踏まえ、避難所としての整備が求められている。幼児から高齢者、障がい者、アレルギー疾患のある方等にも対応するため、食事の面、施設の環境整備についての今後の計画の考えを問う。 |
(1)近年の異常気象を踏まえた、避難所の施設整備計画の考えは。 (2)アレルギー疾患の方への食事対応の考えは。 (3)長期避難を見据えた備品等の対応は。 |
※一般質問の発言予定時間は進行により変更することがあります。