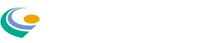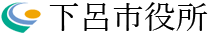本文
市政の課題に対する提案書を提出
「市政の課題に対する提案書」を提出しました
令和6年9月30日、下呂市議会から「市政の課題に対する提案書」を下呂市長に提出しました。
提案書は、新年度予算編成や下呂市第三次総合計画の策定に反映いただくよう常任委員会ごとに議員間で協議を行い作成しました。
今後は提案内容に即した視察等を行い、年内にはより具体的な提言書を提出する予定です。
提案書(民生教育まちづくり常任委員会)
1.あさぎりサニーランド移転新築の早期実現を
昭和57年に新築されたあさぎりサニーランドは、築42年を経過し、雨漏りが多発するなど施設の老朽化は激しく、専用の休憩室が無いなど職員の働く環境も整っていません。また、現所在地は飛騨川浸水想定区域に指定されており、防災面でも大きな問題があり、平成30年、令和2年・3年の豪雨では、入所者の方々は指定避難所に避難されています。市においても、移転新築の必要性は認識され、今年3月には「あさぎりサニーランド移転基本構想」を策定されましたが、120人ほどの入所者の方々やご家族に安心して生活していただき、下呂市の介護サービス等の基幹施設として引き続き大きな役割を担っていけるよう、以下のとおり提案します。
(1) あさぎりサニーランドの移転先用地を早急に決定し、早期完成に向けたスケジュールを策定すること。用地選定に当たっては、防災面の安全性を最大限考慮すること。
(2) 新施設については、他の事例を参考に、木のぬくもりを感じる木造とすることを検討すること。
(3) 用地決定後においても完成までは5年以上の期間を要することが想定されるため、現在のあさぎりサニーランドについては、費用対効果を考慮しつつ、必要な改修等を実施すること。
(4) かなやまサニーランドのサテライト化については、職員の確保、地理的条件等を慎重に検討すること。
2.猛暑から市民を守るために
令和6年4月から熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。自助による熱中症予防行動を原則としながらも、共助や公助として最大限の予防行動が実践できるよう、自治体による支援も求められています。乳幼児から高齢者までの市民を猛暑から守るため、以下のとおり提案します。
(1) 地域の集会施設等をクーリングシェルターとして活用し、併せてエアコン等の整備や電気代を含む施設の維持・管理費に係る補助等制度を創設すること。
(2) 小学生の帰宅時間帯は気温が高い時間帯と重なるため、徒歩通学を懸念する保護者の声も多い。バス通学運用の見直しや日傘の活用推進など、子どもたちの命を守る取り組みを実施すること。
(3) 公園や子育て支援センターなどの施設においても、これまで以上に暑さ対策に配慮し、市民にとってより魅力的な施設となるよう運用面も含めた環境整備を進めること。
3.市民の生活の足となる公共交通の確保・充実に向けて
過疎化や少子高齢化等により、従来の公共交通の維持が困難となっています。子どもや高齢者を含め、市民誰もが暮らしやすい下呂市の実現のため、以下のとおり提案します。
(1) 高齢者や免許を持たない市民の日常生活の利便性を向上させるためには、非営利ライドシェアやMaaSを活用したドア・ツー・ドア交通の実現や目的別の移動手段の確保が必要です。
非営利ライドシェアの導入には、法的規制や安全性の課題がありますが、地域の絆を活 かした「互助交通」としての新たな可能性が期待されるため、下呂市第三次総合計画に合わせた新たな「下呂市地域公共交通網形成計画」に組み込むこと。
(2) 今年度新設された訪問型サービスDは、介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行う移動支援であり、ボランティアが外出時に移送前後の補助を行う公共交通を補完する手段となるため、使用できる車両の確保に向けた取り組みを実施すること。
(3) 他地域では、「どこでも乗れてどこでも行ける」を目標に、路線バス、スクールバス、デマンドバス等を一体で活用し、運行経費の異なる民間の路線バス等に運行補助費を設けるなど、市内同一料金を実行していますが、下呂市でも料金均一化に向けた取り組みを実施すること。
提案書(総務産業建設常任委員会)
1.防災・減災対策のさらなる強化に向けて ~能登半島地震を受けて~
世界的な気候変動による気温の異常な上昇、昭和から平成時代とは比較にならない集中豪雨、頻発する地震等、市民の日々の暮らしは迫りくる自然災害に常に脅かされています。今年元日に発生した能登半島地震では、道路が寸断されたため多くの集落が孤立し、災害救護班の到着まで非常に時間を要する結果となりました。下呂市から元日に救援に向かった部隊が到着したのが4日の昼であったという具体的な例もあります。孤立した地域の住民は、救援部隊が到着するまで、自分たちだけの力で生き延びていかねばなりません。 阿寺断層の真上に位置する下呂市も地震災害は決して他人事ではなく、災害の発生状況も地形上、似たような状況に陥ることは十分推測できます。そのためにも私たち市民は、彼の地で起こったことからしっかりと学び、平常から自助・共助を意識し、来るべき災害に備える必要があると考えます。このような観点から以下について提案します。
(1) 市民の自助・共助に対する意識改革を進めること。
・具体的なガイドラインの策定(自主防災組織による救助作業・避難所運営等)
例)倒木で道路が寸断された場合の地域の林業従事者・経験者の関わり方
例)タイヤショベルを所有している農家の災害時の関わり方
・防災訓練の抜本的な見直し(自助・共助意識を喚起させる訓練の提案)
(2) 建設機械リース会社との災害支援協定を締結すること。
(3) 被災地に派遣された職員の報告を基に有事の際、有効に救援部隊が機能できるよう受入れ体制の見直しを早急に行うこと。
・指揮所の設置場所、宿泊施設の確保等
(4) 安定したライフラインの確立に向けた整備と備蓄のさらなる拡充を行うこと。
・指定避難所における発電機、空調設備の整備
・快適な居住スペース、トイレの確保等
2.農地保全が末永くなされていくために
少子高齢化の進む当市は、農業従事者も極端に少なく、ほんの2%程度の人数で広大な農地を守っています。さらにその少ない従事者も高齢化が進み、本来であれば親から子へ、子から孫へと継承されていくはずの農地が、都市部への人口流出、生活様式の変化等の時代の流れにのまれ、耕作放棄地と名を変えており、同時に本来であれば、年間の農作業の中でそれぞれの農家の手によって適切に管理されてきた農道、畦畔、用排水路等も同様に荒廃し景観を損ねています。一方でこのような状況に歯止めをかけようと、各地域で農地を引き受ける担い手や、農地を集積して集落営農を立ち上げ守っていこうとする動きも出てきています。しかしながら、この担い手と呼ばれる方々、また集落営農組織においても深刻な後継者不足や肥料・燃料等の値上げによる生産コストの増大、定期的な耕作機械の更新に係る莫大な費用等、課題が山積しています。まさに現在は農地の存続以前に、それを守ろうとしている組織自体の存続が危ぶまれる危機的状況と言えます。このような中にあって、行政としてもっと積極的にこの問題に関わり持続可能な農地保全に向けて、しっかりとした施策を打ち出していく必要があると考え、以下について提案します。
(1) 行政が中心となって、担い手・集落営農組織の協議会等を立ち上げ、意見交換や事例紹介、経営相談等を実施し、活性化を図ること。
(2) 担い手・集落営農組織、小規模農家および環境保全を目的とした地域活動に対する市独自の支援事業を創設すること。
(3) 国庫および県単土地改良事業補助金交付要綱の基準を満たさない小規模な団地における圃場整備を対象とする市独自の補助制度を創設すること。
市政の課題に対する提案書(令和6年9月30日提出) [PDFファイル/260KB]