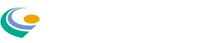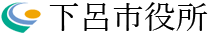本文
12月定例会一般質問の内容(質問要旨と質問項目)
本定例会では、一般質問で13人の議員が市政について質問を行います。
一般質問
12月12日(木曜日)午前9時30分開会
|
【予定時間】 発言議員 |
質問要旨 | 質問項目 |
|
【午前9時30分から】 桂川いずみ |
1.総合防災訓練の重要性について 今年度の9月1日下呂市総合防災訓練が「台風接近の為に中止」となりました。安全を考慮した判断で有ったと思います。 11月5日には全国一斉安全行動訓練の実施に合わせ「げろ市民一斉安全行動訓練」の広報無線が流れました。後日地域の中には自主訓練をされた所もあったと伺いました。 能登半島地震、奥能登豪雨の災害を踏まえ、全国的に災害に対する意識や危機感が非常に高まっています。 防災対策、避難訓練の重要性、市民一人ひとりの意識の向上、自助かつ、地域共助の取り組み、避難箇所の柔軟な見直しもされているとは思います。 その反面、高齢者が多い地域性さらに外国人労働者が増加している側面もあります。このことから、市が主導の総合防災訓練が必要であったのではないかと考えるので市の考えを問う。 |
(1)総合防災訓練の予備日を設けてなかった理由をお聞かせ下さい。 (2)次の総合防災訓練は令和7年度の9月実施なのでしょうか。 (3)災害時におけるオール下呂体制の進捗状況をお聞かせください。 (4)高齢者には一般の方と区分して、福祉的配慮が必要と考えられますが、何等かの施策はお考えでしょうか。 (5)下呂市での外国人就業者や観光客の方は年々増加傾向に在りますが、緊急時防災対策の配慮はされていますか。 |
|
2.空き家の把握の進捗状況について 空き家法では、市町村は空き家の状態や管理状況を把握する調査は、努力義務でデータベース化はされていないと言う事でした。 6月の一般質問で、全市内を対象とした空き家調査を実施して、データベースを整備する必要が有ると回答されましたが、その調査結果をもとにしたデータベース化の進捗状況を問う。 |
(1)空き家件数の現状について問う。 (2)前回、回答にあった空き家の利活用に対するワンストップで対応の仕組みは構築されましたか。 (3)空き家の売却や賃貸を希望されている方が、空き家紹介制度を知るために当局はどの様な広報活動をされていますか。 (4)空き家調査において、特定空き家における、所有者への補助制度など行政が出来る伝達・支援の状況はいかに。 |
|
|
【午前10時10分から】 加藤久人 |
1.指定管理者制度について 下呂市では32施設の運営が指定管理者制度に基づき、各民間事業者等に任されている。 指定管理制度は、本来民間のノウハウや技術を活用することで公共施設の運営をより効率的に行う事が目的とされている様に思える。 しかし、まだまだ民間活力が十分活用できていないように思えるので、そのあたりについて市当局の考えを問う。 |
(1)一部の協定書を見ると、余剰金が発生した場合は返金する協定であるが、これではモチベーションが上がらないように思えるが、そのあたりの考えはいかに。 (2)下呂市公共施設等総合管理計画には、民間活力導入と謳ってはあるが、協定書の中身は条例等での縛りも多く、十分民間の力が発揮出来る内容ではないように思えるが、そのあたりの考えはいかに。 (3)今後、公民連携が図られようとしている中、民間の力をフルに活用する必要性があると考えられるが、今後の方向性はいかに。 |
|
2.地震における液状化現象について 先日、能登半島地震の被災状況を視察する機会を得て、宝達志水町にて液状化現象により、基礎基盤から傾いている現場を目の当たりにして来た。 また、11月9日に開催された下呂市防災まちづくり講演会にて阿寺断層帯における地震の際には、下呂温泉街でも液状化が起こる可能性が高いとの説明を受けた。 そこで、液状化現象への対策について市当局の考えを問う。 |
(1)下呂温泉街においても震度5強以上の揺れが起こった場合、液状化現象が起こり、高層建物も被害に遭う可能性があるが、その場合の被害状況は想定しているのか問う。 (2) 液状化現象の恐ろしさをもっと周知するべきと思うが、考えはいかに。 |
|
|
【午前11時00分から】 森 哲士 |
1.御嶽山の国定公園新規指定について 2022年6月に御嶽山が国定公園の新規指定候補地に選定されたが、その後の進捗状況を問う。 環境省、岐阜県、長野県、高山市との選定に対する連携協議の状況と地元関係団体との意見を踏まえた今後の対応と御嶽山を取り巻く自然資源の活用と施策について問う。 |
(1)環境省が文献調査及び現地調査を昨年調査し公園指定書及び公園計画書の大枠を作成したが、その内容と下呂市の考えは。 (2)自然公園制度の概要と、自然保護と経済発展のバランスを考慮し、計画的に整備を行うため、自然と観光・文化の融合した価値を構築する上で、規制や手続きについて地主や地元産業等に係る調整が図られているか。 (3)2023年、飛騨小坂~自然のめぐみを体験、滝めぐり、湯めぐり「NEXT GIFU HERITEAGE~岐阜未来遺産」とのプロモーションの展開や通信環境、道路、駐車場等、今後の施策は。 |
|
2.消防団活動の取り組みと課題について 令和4年度に年額報酬と出動報酬が見直され、同時に個人支給とすることとなったが、報酬見直し前と比べ活動に対し問題点や課題などが生じていないか。 持続可能な消防団とするため、団員、家族、職場に対し活動への理解を求める取り組みや、技術レベルの均一を図るための取り組み、体制維持・強化の議論がなされているか。 |
(1)「年額報酬」と「出動報酬」の2種類あるが、それぞれの趣旨(消防団員に何を求め、どういった目的、どういった活動の対価として支給しているのか)について説明を求める。また出動報酬の対象とならない活動はあるか。あればその活動はどういったものがあり、なぜ対象とならないのか説明を求める。 (2)報酬見直しと個人支給となって3年目を迎えたが、年額報酬の支給方法については一定のルールを設ける必要があると考えるが、これまで又は今後において何かしらの対策が検討されているのか説明を求める。 (3)コロナ禍で、操法大会や訓練、各行事ができない時期があったが、その後、各活動で団員の団結力など変化はないか。また再任用基本団員及び災害支援団員の協力により消防力の持続維持がされているといっても過言ではないが、通常基本団員の減少による消防力の低下を招くわけには当然いかず、訓練・行事での出動状況と操法訓練や大会の課題と今後の在り方について問う。 |
|
|
【午前11時40分から】 桂川融己 |
1.市民の声を反映させる仕組みについて アンケートやパブリックコメント等の手法を通じて、広く市民の声に耳を傾ける仕組みは市民向けPRの役割も担う重要な取り組みである。一方で、回答しにくいもの、結論ありきのように感じられるものもあるなど、運用の難しさも感じる。市民の声を市政運営や広報に反映させるための取り組みにつき、当局の考えを問う。 |
(1)広く市民の声を聞く仕組みとして、どのような手法があり、どのように運営されているのか。 (2)市民の声を聞く際、どのような点に留意すべきだと考えるか。アンケートの運用ルールについて、条例や運用規定などで定められたものはあるか。その必要性についてはどう考えるか。 (3)広報モニター制度は運用されているのか。今後の方向性は。 |
|
2.南飛騨Art Discoveryの成果と方向性について 37日間の南飛騨Art Discoveryが閉幕した。芸術祭には、市内外から多くの人が会場に足を運び、アートを通じて、下呂の自然・文化・歴史に触れていただく貴重な機会となった。今回の成果と、今後の方向性について当局の考えを問う。 |
(1)来場者数、パスポート販売数等を含む定量的な成果は。 (2)総合ディレクターの北川フラム氏の感触、関係者の手応え、来訪者の声などによる定性的な成果は。 (3)今後の方向性について、市長の考えは。 |
|
|
3.公共施設の適正化に向けた取り組みの方向性について 第三次総合計画(案)で「公共施設の再配置・適正化」への言及があった。利用率等の現状、今後の維持管理体制、老朽化対策、財政面への影響などを鑑みても、持続可能な市政運営を考える上で避けて通れない課題である。当課題への検討状況や取り組みの方向性につき、当局の考えを問う。 |
(1) どのような課題認識を持っているのか。持続可能な公共施設のあり方を考える上での課題は何か。 (2)どのような判断軸で検討を進め、対応の優先順位を付けていくのか。今後の取り組みの方向性は。 |
|
|
4.若手職員が挑戦・活躍できる風土づくりの進捗状況について 前回、職員のなり手不足・人材育成対策として、若手職員が挑戦・活躍できる風土づくりについて、質問させていただいた。新卒採用や若手職員による取り組みなど、その後の対応について問う。
|
(1)下呂市職員採用は、予定数に達しているのか。 (2)若手職員によるプロジェクトについて、デザイン部会の取り組みなどの紹介もあったが、その後の進捗状況は。 |
|
|
【午後1時30分から】 中島ゆき子 |
1.地域医療の要である市立金山病院の今後と、下呂温泉病院との連携について 市立金山病院は、令和6年12月末をもって4階の療養病棟を閉鎖し、3階の一般病棟だけになる。 医師不足、看護師不足が課題となっているが、今後の病院運営について問う。 |
(1)療養病棟は、看護師不足により閉鎖されると議会は説明を受けていたが、住民へは下呂温泉病院に療養病棟が開設されたことも閉鎖の理由と説明されている。両病院の間での調整はできなかったのか。 (2)療養病棟を閉鎖することにより、看護師不足は解消されるのか。 (3)療養病棟の閉鎖により、病院の収入は減収すると考えられるが、経営改善の方策は。 (4)市立金山病院の今後の運営について、どのような検討がされているのか。 (5) 現在、下呂温泉病院の療養病棟の稼働率は。 (6)下呂温泉病院との医療連携は重要である。先ず何から取り組んでいくのか。 |
|
2.今年度から取り組まれようとしている新1年生へのランドセルの無償配布について 令和8年度からの新1年生は、希望者のみランドセルを無償配布し、希望しない場合は何の補助も行わない。このことについての考えを問う。 |
(1)ランドセルの無償配布についての要綱の内容は。 (2)令和7年度の新1年生は、無償のランドセルを希望しない場合は1万5千円の補助があるが、令和8年度以降に補助がないのはなぜか。 (3)子育て支援について、市はどう考えているのか。 |
|
|
【午後2時10分から】 田中喜登 |
1.第三次総合計画の策定について 今定例会において、下呂市第三次総合計画基本構想の策定についての議案が上程された。その中の2項目目にまちづくりの理念が示され、「未来につなぐ ふるさとづくり」として市民一人ひとりのウェルビーイングを追求することを最優先に考えて未来にむけたまちづくりを進めていくとある。ここに関連し、2点伺う。 |
(1)今年10月に発表された地域ブランド調査2024魅力度ランキングで下呂市は55位から49位とランクアップし、県内の市町村では1位となっている。認知度、情報接触度、居住意欲度、観光意欲度等、様々な調査があるが、この結果についてどのように考えているのか。 (2)ウェルビーイング指標を見ると主観データが客観データの内側に収まっており、周囲の評価が高い割には、実際に住んでいる人の満足度が低い印象を受ける。この部分をどう評価し総合計画にどう反映していくのか。 |
|
2.旧JAひだ下呂支店跡地利用について 解体工事が完了し、更地となった旧跡地について、9月議会で駐車場の創設を予定しているとの答弁があったが、どのようなものになるのか伺う。 |
(1)既存の駐車場と一体化させるのか。 (2) 北側に市道があるが、道幅が狭く通りにくいという意見をよく耳にする。整備に合わせて改良する予定は。 (3)庁舎との連結、および庁舎北側に出入口を新設するなどの計画はあるのか。 |
|
|
【午後3時00分から】 高井範和 |
1.県立下呂温泉病院での出産体制について 県立下呂温泉病院の産婦人科には3名の医師がお見えになるが、人員的な問題から24時間体制での出産受け入れ対応が厳しい状況になり、現在産婦人科では昼間の妊婦健診等は受診可能だが、出産については妊婦が希望する病院と連携しているとのこと。この現状から産婦人科の医師招聘、子育て・移住について市の考えを問う。 |
(1)県立下呂温泉病院の産婦人科の現状に対する市の見解は。 (2)同院の産婦人科医師の招聘に向けた市の取り組みは。 (3) 同院にて現在、出産できる体制が整っていないことが子育てや移住を考える方にとってマイナスイメージにならないように、現状の取組等を広く市民に伝えるべきと考えるが市の見解は。 |
|
2.能登半島地震を踏まえた防災体制の整備について 能登半島地震は元日という特別な日に発生し、隣県でもあり、防災について深く考える一年になった。そこから得られた経験や教訓、自治会の備蓄品や防災装備に関するアンケート結果は、今後の下呂市の防災に活かさなければならない。 その取り組み状況と今後の計画について問う。 |
(1)災害支援活動に出向かれた市職員の方々からの災害対策に関わる提案や得られた教訓の実施に向けた取り組みの進捗状況は。 (2)自治会に対する備蓄品調査結果をどう捉えているか。 (3) 国・県、民間ボランティアなど外部からの支援の受け入れ体制の整備状況は。 |
12月13日(金曜日)午前9時30分開会
| 時間 | 発言議員 | 質問事項 |
|
【午前9時30分から】 尾里集務 |
1.公共施設の利用におけるデジタル化の進捗について 市の公共施設の利用者の手続きにおいて、施設の予約は電話や直接管理者の所に予約に行き、利用日は鍵を借りに行くということになっている。このようなことから利用者の負担軽減、管理の簡素化などを考え、デジタル化にできないか。
|
(1)公共施設の鍵の管理をスマートロックに出来ないか。 (2)予約状況などもインターネットを活用し、パソコン、携帯から確認できないか。 (3) 利用報告書なども携帯から出来ないか。 |
|
2.将来の小中学校のあり方について 今後下呂市の人口減少、少子化に伴う学校の小規模化がさらに進む事が予想される中、将来にわたって子供たちが学校教育を受けるにあたり、保障していく観点から学校の適正配置のあり方について検討していく事が必要である。 市は学校の設置者として、適正配置を円滑に進めていく考えは。
|
(1)市が行ったアンケート結果を踏まえての考えは。 (2)中学校の部活動の地域移行についての考えは。 |
|
|
3.農林業を持続させるために 農林業を維持継続していくことにより、地域を守っていくことに繋がると思います。ところが高齢化、担い手不足などにより、荒廃農地の拡大が予測されます。こうしたことからその対応策として、農地集積、担い手確保などの課題は。
|
(1)新規就農者の現状と課題。 (2)小規模農家への支援策は。 (3)荒廃農地の現状と課題は。 (4)下呂市の山林を守るべく林業従事者の確保は。 (5)下呂市森林計画の進捗状況は。 |
|
|
【午前10時10分から】 大西尚子 |
1.地域福祉の課題について 下呂市では地域福祉の向上を目指し令和4年度から令和8年度までの5か年計画で第4期下呂市地域福祉計画を策定しました。地域福祉活動計画も一体的に策定されており、今後の下呂市の地域づくりに重要な役割を担うと思われます。市として支援や今後の課題について質す。
|
(1) 地域福祉計画の推進について第4期の計画が3年目を迎えるが、取り組みは順調に進捗しているか。 (2)地域福祉活動計画の推進役を果たす役割は重要と思われるが、推進体制に対し市としてどのような支援を実施し、十分な支援を実施しているか。そして課題は。 |
|
2.小坂診療所について 小坂診療所はこれまで形態を変えつつ小坂や萩原北部地域の診療や入院拠点としての役割を果たしてきた。医療機関、介護サービス事業所として、今後の人材の確保の方針について市の考えは。 |
(1)小坂診療所のこれまでの運営状況はどのようになっているのか。市の医療機関、介護サービス事業所として今後どのように運営するのか。 (2)医師の人材確保も難しいと聞くが、市としてどのように取り組んでいくのか。今後の人材確保の方針についてどのように考えているのか。 |
|
|
3.歯周疾患検診の受診率について 下呂市の歯周疾患検診受診率は県内平均と比べてかなり低い。全身の健康を保つ観点からも歯と口腔の健康づくりへの取り組みが必要と思われる。健康寿命の延命、医療費の削減にもつながる歯周疾患検診の受診率を上げるための、市としての取り組みは。
|
(1) 歯周疾患検診とぎふ・さわやか口腔健診と妊婦歯科検診の受診率はどのように推移しているのか。受診率をあげるための具体的な取り組みは。 (2)歯周病を有する者の減少のために取り組んでいる事業は。 |
|
|
【午前11時00分から】 田口琢弥 |
1.災害時における避難所等の災害用トイレについて 多くの災害被災地や視察に行った能登半島地震被災地で一番不自由だったのは「トイレ」であった。 そこで、下呂市における災害時のトイレ対策は。
|
(1)災害用トイレの内訳と現在の備蓄数。 洪水・地震等で避難想定人数に対して備えるべき備蓄数は。 (2)市内マンホ-ルトイレの設置場所と数。 マンホ-ルトイレの取り扱いは。 (3)年間100万人近く観光に訪れる下呂市。 国内外からの多くの観光客や市内在住の外国人の方々に対する災害時のトイレ対策は。 (4)下呂市の「下水道総合地震対策計画」策定についての考えは。 |
|
2.下呂市クアオルト健康ウオーキングについて 令和6年4月から市民皆さんやクアオルト健康ウオーキング参加者の健康増進・健康寿命延伸を目指して開催されているが、内容と方針について問う。 |
(1)現在のクアオルト健康ウオーキング参加者数は。 また、今年度の参加人数の目標は。参加を促すための周知方法は。 (2)現在のガイドの人数とガイド報酬、また、クアオルト健康ウオーキング開催までにかかった費用は。 (3)先日 クアオルト発祥の地である「ドイツ」に視察されたが、今後下呂市クアオルト健康ウオーキングで取り入れていくべきことは。 |
|
|
【午前11時40分から】 下平裕次郎 |
1.子どもおむつ無料定期便導入について 子どもおむつ無料定期便は、経済的支援で月3,000円程のおむつなどの子ども用品が市から贈られるため、購入の必要が無くなる。 寄り添う支援は親が孤立を感じやすい時期に子育て経験の近い専門職員などが直接自宅へおむつなどを配達することで、その際に子どもの様子も含め、相談事などを行うことで、寄り添える支援となる。 2つの効果などが考えられるが、今後の導入に向けての方針を問う。
|
(1)現在、未満児の保護者に対する訪問ケアの取り組みはどのようなものがあるか。 (2)現在、市が実施している妊娠から出産、子育てに関する経済的支援で特徴的な取り組みはどのようなものがあるか。 (3)市内で未満児の健康状態や生存の把握方法はどのような取り組みがあるか。 |
|
2.学校給食及びこども園でのふるさと給食地産地消給食について 下呂市は地元の農家さんなどが作った野菜や伝統料理、下呂温泉で人気デザートなどを「ふるさと給食」として地産地消を推進しているが、その成果と今後の方針について問う。 |
(1)ふるさと給食では子どもたちにどのように説明をして、食育へとつなげているか。 (2)食材を確保するために課題はあるか。 (3)給食でのお米を全て下呂市産へ変更することは必要量の関係からも可能であると考えるが、実施するにはどのような基準があるのか。 (4)今後、学校給食を核とした下呂市全体の地産地消を推進していくことが、重要であると考えるがどのように考えているか。 |
|
|
3.下呂市内でのイベントやマラソン大会の助成について 下呂市内でも多くの素晴らしいイベントやマラソン大会などが開催されているが、その助成などの支援や今後の方針について問う。 |
(1)先日、民間主催のノース御嶽マラソン、飛騨川公園で開催されたハロウィンイベントや消防本部主催の防火安全フェスタなど市内では数多くのイベントが行われた。 今後、市として、サポートなどの補助についてどのように考えているか。 市が主催するイベントなどの成果と課題は。 (2)イベント開催には、多くのノウハウや情報発信の難しさがある。そのような課題を専門の任期付職員などにより、相談窓口を作るなどソフト面での支援は考えているか。 |
|
|
【午後1時30分から】 鷲見昌己 |
1.地域における救急医療体制の強化について 下呂市では、人口減少や高齢化が進む中、医療資源の確保や医師不足が深刻化しており、救急医療体制の維持・向上が大きな課題となっています。特に、脳疾患や心疾患といった緊急事態に迅速に対応するためには、ドクターカーやドクターヘリの活用が重要であると考えられますが、現在の運用状況や今後の方針についてお伺いします。 また、隣接市の救急病院へのアクセス改善も課題であり、搬送時間短縮や交通手段整備に向けた市の取り組み状況についてお伺いします。 さらに、救急医療体制を強化するためには、限られた医療資源を有効活用する必要があると考えますが、市の具体的な計画や方針についてお伺いします。 |
(1)救急搬送の現状について。 ・令和5年の発生件数(脳・心疾患別) ・搬送先 件数と施設名 ・病院収容までに要する時間(現場待機時間の平均も説明) (2)搬送時間短縮に向けた取り組みについて。 (3)ドクターカー、ドクターヘリ連携について。 ・利用実績、効果 (4)救急医療体制の強化に向けての取り組みについて。 ・下呂温泉病院、金山病院の連携及び広域連携について ・アクセス改善に伴うインフラ整備の現状について |
|
2.公共交通について 現在の市内のバス運行状況は、市営のコミュニティバス、デマンドバス、民営の路線バスが運行されている。しかし、竹原地域では乗政三ツ石地区や御厩野北部などの山間部では、停留所までの距離が遠い地域に住む市民も多い。 また、高齢化が進み、遠方の停留所まで歩いていくことが困難な市民も多く、免許返納ができない要因にもなっていると考えられる。 また、部活動やクラブ活動の移動手段も家族に頼るほかないのが状況です。今後の公共交通整備に向けた取り組みについて伺う。 |
(1)竹原地区をはじめとした交通空白地域でのデマンドバス運行ができないか。 (2)デマンドバスを活用し、お年寄が外出を楽しむことが可能になるよう、買い物ツアーや温泉ツアーなどの短時間バスツアーを企画してはどうか。 |
|
|
【午後2時10分から】 今井政良 |
1.新年度予算編成について 市民が安心安全な生活環境で生活できるための予算編成が必要である。 近年の異常気象対策や物価高騰支援、市としての重要課題である少子高齢化に伴う人口減少問題等に対する対応策が求められている。 そこで各事業の方針について問う。
|
(1)能登半島地震を教訓とした災害復旧体制。 (2)長期避難所としての施設整備(エアコン設置等)。 (3)長期間を想定した備蓄品の確保。 (4)医療連携体制。 (5)安定した雇用確保のための医療助成(帯状疱疹ワクチン等)。 (6)物価高騰に対する支援策。 (7)未満児保育料及び給食費無償化への考え。 |
|
2.地域公民館の有効活用について 下呂市の課題として、少子高齢化が挙げられる。それに関わる取り組みとして、子どもとその保護者に向けては、「ニコリエ」の設置や子育て支援センター主催の集会などが行われている。また、高齢者に向けては社会福祉協議会主催のサロン、教室、見守りネットワークなどがある。しかし、高齢者と子どもが自由に集える場がない。 子どもとふれあったり、話したりすることを楽しいと感じる高齢者は多いと思う。また、子どもも高齢者から豊富な人生経験や伝統文化などを学ぶことができる。 そこで、地域の交流の場として、また、放課後や休日の遊ぶ場として地域公民館の有効活用について伺う。 |
(1)放課後や休日など各地区の公民館開館に対する支援の考えについて。 (2)夏場の登下校時や、高齢者の暑さ対策としてのクーリングシェルターとしての活用について。 (3)公民館を活用した、高齢者と子どもがふれあうサロン開催について。 |
※一般質問の発言予定時間は進行により変更することがあります。