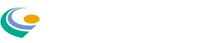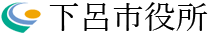本文
9月定例会一般質問の内容(質問要旨と質問項目)
本定例会では、一般質問で12人の議員が市政について質問を行います。
一般質問
9月16日(火曜日)午前9時30分開会
|
【予定時間】 発言議員 |
質問要旨 | 質問項目 |
|
【午前9時30分から】 桂川いずみ |
1. 地域集約化の推進について 下呂市は広大な土地に集落が点在しており、人口減少と高齢化が進行する中で、持続可能な地域運営が課題になって来ていると感じます。 令和6年の能登半島地震では、集落が点在していることが災害対応を困難にし、住民の孤立や支援の遅れが深刻化したのではないかと感じました。 こうした教訓を踏まえ、下呂市においても災害対応力を強化するとともに、日常の暮らしや行政サービスの質を高めるための「地域集約化」について検討を進めるべきだと考えます。 地域集約化は、防災の拠点の整備だけではなく、医療・福祉・交通・教育など様々な機能を効率的に配置し、住民の安心と利便性を高める施策であり、財源と人材を有効に活用しながら、地域のつながりを維持し、誰もが取り残されないまちづくりを進めることができます。 この施策において、今後の具体的な方針と地域住民との合意形成のあり方について、当局の見解をお伺いします。 |
(1)能登半島地震の教訓を踏まえ、災害対応力の検証と課題の認識について問う。 (2)人口減少が進む中、コンパクトシティなど地域機能を集約する必要性について当局の基本的な考え方は如何に (3)地域機能の集約化について、具体的な対策や構想があれば、市民の皆さんがイメージしやすいように分かりやすくご説明ください。 |
|
2.第三次総合計画における今後の自治会のあり方について 市内では各自治会が地域の魅力を活かした観光誘致や文化・伝統の継承、そして住民主体のイベント開催など、地域活性化に多大なるご尽力をいただいております。そうした地域の皆様の取り組みに感謝しております。 しかしながら、高齢化や人口減少が進み、地域活動の担い手不足といった深刻な課題が地域行事の継続にも影響を及ぼしているという声を多く聞きます。 今後も持続可能な形で地域を支えていくためには、行政による支援や新たな連携体制の構築が必要ではないでしょうか。 そこで市としては自治会にどのような役割を期待されているのか。また、担い手不足といった喫緊の課題に対してどのような支援策をお考えなのかお伺いします。 |
(1)市の総合計画において、自治会はどのような役割を担うことになっていますか。 (2)自治会の担い手不足や高齢化が進んでいる問題に対し、市はどのような支援を考えていますか。 (3)地域コミュニティ・自治会運営維持のために市はどのような組織づくりを支援する予定ですか。具体的な施策を教えてください。 |
|
|
【午前10時10分から】 加藤久人 |
1.デマンドバスの今後について 昨年10月より運行されているデマンドバス金山循環線の今後について考えを問う。 |
(1)6月2日~30日までの期間限定で、市立金山病院・マツオカ金山店・金山振興事務所の3カ所の指定施設からバスを利用する方を対象とした無料券発行事業が行われた。その結果75人の利用者があったとの事であるが、この事業の目的とその成果について問う。 (2)バス路線を廃止するかどうかの目安は、1日当りの利用者数24人、1便当たりの利用者数4人とされているが、令和7年4月~7月の4カ月間の実績では、1日平均16.3人、1便平均2.7人となり目安を下回ってしまっている。 今後の方向性はいかに。
|
|
2.庁舎の有効活用について 金山振興事務所庁舎は平成3年に建設された耐震性のある建物で、延べ床面積は4,023平方メートルあり下呂庁舎より広い庁舎である。 しかし、庁舎内には活用されていないスペースが大変多く見受けられ、有効に活用できていない様に感じるが、今後の活用方針を問う。 |
(1)4階の一部は郷土館として利用されているが、来館者にとって使いやすい施設とは言えないように思われる。この郷土館の今後の方向性についての考えを問う。 (2)4階には下呂庁舎にも引けを取らない立派な議場や複数の会議室があるが、いずれも倉庫のような状態となっている。 又、2階の大部分も使用されていない状況である。 これらのスペースは、宝の持ち腐れの様に感じるが、今後の活用方法について考えを問う。 |
|
|
【午前11時00分から】 高井範和 |
1.小さな担い手支援金(農業機械購入補助金)の活用状況と今後について 農業従事者の高齢化が進む中、高額な農業機械の購入・更新が離農のきっかけとなり、耕作放棄地が増加することが懸念される。この対策として今年度創設された「小さな担い手支援金」について現在の利用状況は。 また、この制度は来年度以降も継続すべきだと考えますが、当局の考えを伺う。 |
(1) 今年度創設した「小さな担い手支援金」の申請状況はどうなっているか。 (2)この支援金制度について、市民からはどのような声が届いているか。 (3)この支援金制度の改善すべき点と、今後の方針について伺う。 |
|
2.家庭ごみの減量化・資源化に向けて 下呂市クリーンセンターに収集されるごみの約9割が焼却処分され、その約半分が家庭から排出されるごみであると伺っている。 この現状を踏まえ、家庭ごみの減量と資源化をさらに推進するためには、市民一人ひとりの意識を高め、協力を得ることが不可欠であり、市民と行政が一体となってこの課題に取り組む必要があると考えますが、市の今後の具体的な方針や取り組みについて当局の考えを伺う。 |
(1)令和5年度から家庭ごみの出し方が変わっているが、その後の排出量はどのように変化したか。 (2)「無料もえるごみ処理券」を配布する目的と、氏名を記入する目的は何か。 (3)家庭から排出される廃プラスチックや生ごみ、空き缶などの分別収集、また、ごみの減量化・資源化に向けた取り組み状況を問う。 |
|
|
【午前11時40分から】 田中喜登 |
1.こども園の今後について 市内の「保育園」が、いつの間にか「こども園」という名前に変わっていることにお気づきでしょうか。現在、下呂市には「保育園」はなく、「こども園」または「子育て・保育ステーション」となっています。 若い世代の共働き家庭がほとんどである当市にとって、これらの施設はなくてはならない存在です。そこで「保育園」と「こども園」の違い、市内の施設の現状、そして直面する課題について市民の皆様と一緒に確認したいと思い次の3点について問う。 |
(1)こども園と保育園にどのような違いがあるのか伺う。特にこどもや保護者にとってのメリット、および働く保育士の仕事内容について。 (2)下呂市のこども園の現状と特徴や独自の取り組みについて伺う。 (3)人口減少や少子化、保育士不足といった課題に、こども園はどのように向き合っているか。また、下呂市として、保育士を確保するために、どのような対策を考えているか伺う。 |
|
2.下呂温泉合掌村の現状について 令和2年に元職員による使途不明金事件が発覚し、市を揺るがす大問題となったことは記憶に新しいところであるが、その後の経理経過、施設の現状(維持・改修の状況)、今後の施設の課題の3点について伺う。 |
(1)欠損金の処理経過と現状について伺う。 (2)今年度も民族資料館の屋根葺き替えが予定されているが、事件以降の施設の改修はどのように進んでいるか。また、今後の計画について伺う。 (3)当施設は下呂温泉を訪れた観光客の散策スポットとして重要な役割を担っています。今後合掌村がさらに発展していく上での課題や新たに検討している取り組みについて問う。 |
|
|
3.農業支援について 下呂市では移住などをきっかけに新規就農者の実績が堅調と聞いており、人口減少の抑制・農地保全・担い手確保の観点から大変喜ばしいことと認識している。この新規就農者への支援について次の2点伺う。 |
(1)新規就農者の最近の実績について伺う。 定着率や経営状況など、具体的な指標。 (2)新規就農者には一定年数、支援金が支給されサポートされることは承知しているが、それ以外に例えば各種認証制度取得に対する支援等、具体的に取り組んでいるもの、および今後拡充または追加する支援等があるのか。
|
|
|
【午後1時30分から】 中島ゆき子 |
1.令和7年度一般会計新規事業の進捗状況について 令和7年度一般会計における新規事業は、参議院議員選挙費用や国勢調査などを含め50件ほどある。 金山ふれあいパークの遊具整備事業は、当初の予定より完成が遅れている。この夏に期待されていたミストが出る遊具のお披露目は、10月1日の完成セレモニーまで延期となった。 新規事業の中には、物価高騰や資材不足の影響などにより、改修工事などの遅れが心配されるが、現在までの進捗状況について問う。 また、感震ブレーカー設置費の補助事業は、申し込み方法が変更されたとのことですが、予算の状況と合わせて、詳細を問う。 |
(1)つつじヶ丘公園野球場および萩原南中学校の屋内運動場照明をLED化にする事業の進捗状況は。 (2)小坂中学校、萩原北中学校、萩原南中学校で、それぞれ理科室・音楽室などの特別教室へのエアコン設置の進捗状況は。 (3)保護者の経済的負担を軽減するために市が配布するランドセルについて、令和8年4月の新入学児童の申し込み状況は。 (4)病児保育施設の整備を進めており、下呂市北部の施設は開設したが、かなやまこども園の改修状況は。 (5)感震ブレーカーの普及推進を図る目的で設置費用の補助事業がある。補助の申請方法が7月1日からは「設置後の申請」から「設置前の事前申請」に変更され、締切も9月30日に前倒しされましたが、その理由は。 (6)民生教育まちづくり常任委員会では、今年度の活動方針に「女性が活躍する魅力ある地域づくりについて調査研究を進める」としている。市の女性活躍推進事業の取り組み状況は。 |
|
2.宿泊税の導入に向けた準備状況について 10月1日から導入される宿泊税の準備として、市は、宿泊税を徴収する宿泊事業者に対して宿泊税額の計算、集計、領収書の発行に係るレジシステム等の改修費用を補助するが、現在の申請状況や進捗について問う。 また、市民や観光客の方々へ、宿泊税の導入をどのように周知しているか。 |
(1)レジシステム等の改修費用の補助対象施設は、令和7年2月14日時点では104件であったが、現在の施設の数に変更はあるか。 (2)10月1日の導入に向けてシステムの準備は順調に進んでいるか。 (3)宿泊税の徴収について、利用者が宿泊を予約する際に、どのような方法で周知されるのか。 |
|
|
【午後2時10分から】 鷲見昌己 |
1.地元で働き、暮らすことができる職業の選択肢拡大について 下呂市に住みながら多様な働き方を選べる環境づくりは、人口減少対策と定住促進に不可欠です。テレワークや半農半X、ダブルワークへの支援は、市民生活の豊かさの向上と、地域産業の人材確保を両立できる仕組みと考えます。地元で働き、暮らし続けられるための選択肢を広げる施策について問う。 |
(1)市民が地元に居ながらテレワークで、大手企業等で働ける環境づくりについて、市の現状認識と今後の方針について問う。 (2)森林クレジット付与等を通して連携企業へのインセンティブ創出の考えはないか。 (3)半農半Xやダブルワークがしやすい下呂市独自の雇用支援制度を創出のする考えはないか。 |
|
2.利便性向上に向けた道路網整備について 道路網整備は、市民生活の利便性向上や産業発展、定住促進を進める上で重要な基盤となります。 新規構想と既存生活道の維持改善をどう計画し、優先順位をどう設定するかが重要です。道路網全体の将来像と、整備の優先度について、市の考え方を問う。 |
(1)市民の生活利便性の向上等を見据え、将来の道路網ビジョンをどのように描いているか。 (2)新規道路網や既存生活道路の整備において、市としてどのように優先度を設定しているか。 |
|
|
3.地域の小修繕を行う重機借上げや原材料支給の制度改善について 現在の制度は、主に企業を対象としていますが、地域には重機を持つ個人の方も多くみえます。こうした個人の方々も制度をご利用出来るようになれば、コストの削減と迅速な対応が可能となり、地域からの要望に応える維持管理の力をさらに強化できると考えます。 そこで、自治会が地域の小修繕を行う際に利用できる個人が所有する重機借上げや原材料支給の制度の改善について問う。 |
(1)この制度の実施状況は。 (2)重機を個人で所有する方も対象とする制度改善の可能性について、市の考えはどうか。 |
|
|
【午後3時00分から】 大西尚子 |
1.産前産後ケアのさらなる充実に向けて 下呂市内で分娩できない現状を踏まえ、「ママサポート119」が導入され、妊婦支援の体制が整いつつあります。更なる妊婦への支援策として、宿泊助成制度の導入も有効と考えます。産後ケアの充実や医療機関・地域団体との連携強化を通じて、妊娠期から育児期まで切れ目のない支援について、市の考えを問う。 |
(1)「ママサポート119」について、届出の件数や、利用者から寄せられたご意見やご相談などを問う。 (2)更なる妊婦への支援策として宿泊助成制度も有効と考えるが市の考えを問う。 (3)「産後ケア事業」について、利用件数や利用者の傾向を問う。 (4)「産後ケア事業」について、利用しやすい環境を整えるための方策を問う。 (5)「産後ケア事業」について、移動手段を確保するのが困難な方への支援を問う。 (6)今後、産前産後支援を進めていくうえで、医療機関や地域団体との連携について問う。 |
|
2.地域で支える介護保険制度の持続可能性と課題について 下呂市は令和6年度末に、高齢化率が41.3%となり、高齢者を地域全体で支え合う仕組みづくりが求められています。こうした状況を踏まえ、今後の介護保険制度の運営や地域支援の方向性について、市の考えを問う。 |
(1)介護保険基金の活用を含め、地域支援事業の充実や地域の特性を活かした取り組みが求められています。この点に関する検討状況について、市の見解を問う。 (2)介護人材の確保と職場への定着支援に向けて、市としての取り組み内容や、現場の声を政策に反映させているのか。具体的な事例について問う。 (3)住民負担とサービスの持続性について、保険料の軽減措置や基金活用による保険料上昇の抑制策について問う。また、介護サービス水準を維持していくための方針について、市の見解を問う。 |
9月17日(水曜日)午前9時30分開会
| 時間 | 発言議員 | 質問事項 |
|
【午前9時30分から】 下平裕次郎 |
1.これからの下呂市、日本を担う子どもたちの教育について 近年の社会環境の変化に伴い、学校教育のあり方についても見直す時期に来ている。 学校教育充実への取り組みは人口減少対策の観点からも極めて重要である。「下呂市で子どもに教育を受けさせたい」と思ってもらえるような取り組みが必要と思うが当局の考えを問う。 |
(1)当市での「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実および下呂学の取り組みの成果と今後についてを問う。 (2)異学年学級についての取り組み状況と今後の方向性について当市の考えを問う。 (3) 教育の取り組みの情報発信は子育て世代のUターンや移住定住など人口減少対策にもつながるが、情報発信についての取り組みや課題を問う。 (4) 昨今の猛暑や豪雨といった異常気象への対策として、スクールバスを臨時運行するなど柔軟な運用が必要と考えるが、当市の考えを問う。 |
|
2.「ここで働きたい」と思われる市役所への取り組みについて 現在、多様な働き方が求められる中で、市役所職員においても、家庭や子育てなどに配慮した柔軟な勤務体制の検討が必要だと考える。 市民サービスの質を落とすことなく、効率的かつ持続可能な働き方改革を進めるべきと考えるが、当局の考え方を問う。 |
(1)市役所の開庁時間を短縮することは、より効率的で持続可能な働き方改革につながる可能性がありますが、この点について市はどのように考えるか。 (2)市の窓口がどのように利用されているか、特に混雑する時間帯などを把握するため、市民アンケートやデータ分析は実施されていますか。もし実施されている場合、その結果から市はどのような分析をしているか。 (3)学校の長期休暇において、子育て中の職員が安心して勤務できるような取り組みや課題について問う。 (4)若手職員の柔軟な意見を市政に活かすため、例えば「市長直轄の若手職員チーム」のような仕組みを導入する考えはあるか。
|
|
|
【午前10時10分から】 田口琢弥 |
1.外国籍の子どもたちや保護者について 6月定例会において、市内こども園・小中学校の外国籍の子どもたちについての取り組みを中心に質問しましたが、こども園に入所していない乳幼児を育てる外国籍の家庭には、どのような支援があるのか。 また、令和4年に市が策定した「多文化共生推進基本方針」では、行政の取り組みと課題が示されましたが、現在の進捗状況はどうなっているか。 |
(1)現在の外国籍の乳幼児の人数は。 (2)市内外国籍の保護者の子育てに関する相談窓口や支援等は、日本人の保護者同様に市内各所に設置してある子育て支援センターだと考えるが、現在の外国籍の保護者の利用状況と取り組みは。 (3)日本語でのコミュニケーションが難しい保護者に、子どもの成長と健康を守るための、乳幼児健診などの通知方法と健診の当日、会場ではどのような支援を行っているか。 (4)「多文化共生推進基本方針」策定時に多くの課題が挙げられていたが、現状はどうなっているか。また、外国籍の住民が1,000人を超えた今、新たな課題がないか問う。 |
|
2.水道事業について 全国的に水道管のトラブルが問題となっています。下呂市に於いても大規模な漏水等といった問題は今のところ起こってはいないが、小規模な漏水等は毎月の様に市内各所で起こっています。 そうした中、上水道区域と簡易水道区域の料金格差をなくし統一する為に料金改定もおこなわれました。 また、ライフライン確保の為に上水道施設更新が計画されています。 |
(1)過去5年間の漏水等の発生件数と修繕に要した費用は。 (2)料金改定によって、水道使用料の収入はどの程度増加したか。また、料金改定に関する相談等はあったか。その対応方法は。 (3)令和6年から準備が始まった上水道施設更新事業について、現在の進捗状況と今後の計画は。また、他の地区の更新状況について問う。 |
|
|
【午前11時00分から】 桂川融己 |
1.地域経済の持続性と新しい挑戦を後押しする仕組みについて 人口減少や若者流出が進むなか、地域経済を支える中小企業等の振興は極めて重要である。中小企業・小規模企業振興基本条例に基づく振興計画の策定を契機に、事業者等の関係者が当事者意識をもち主体的に参画できる仕組みを整える必要がある。 また、若者や女性も働きやすい環境づくりや、新たな挑戦を後押しする仕組みを通じて、地域課題の解決につながる取り組みを進めていくことも必要だと考えるが、当局の考えを問う。 |
(1)振興計画の策定に向けた現状と今後のスケジュールはどうか。 (2)各事業者・団体からの意見聴取はどのように進めるのか。当事者意識をもって主体的に参画できるようにするための工夫は何か。 (3)若者や女性にも選ばれるための雇用環境の整備や創業支援について、市はどのような支援ができるのか。具体的な取り組みは。 (4)新たな事業や起業を促すために、ビジネスコンテストやアイデア発表の場を含め、既存企業との連携や地域課題の解決と結びつける仕組みを検討できないか。その際、地域課題の解決に挑むローカルゼブラ的な事業を育てる視点も持つべきではないか。 |
|
2.議論の場づくりと地域運営のあり方について 人口減少や高齢化が進む中、一部地区では自治会・区長制度の維持が難しくなり、地域課題について十分な議論の場が持てていないのではないか。 今後は、住民が主体的に合意形成できる仕組みを整えることが重要だと考える。他自治体では、地域運営組織が移住促進に取り組む事例もある。本市として、地域の意思を尊重しつつ、住民が主体的に議論できる場をどう設け、どのように支援していくのか、当局の考えを問う。 |
(1) 自治会や区長制度の現状と課題を、市はどのように認識しているか。 (2) 地域運営組織が移住促進や住宅管理を担う事例もあるが、本市で同様の取り組みを導入できる可能性はあるか。 (3) 地域が自ら議論し合意形成を図り、多様な役割を担う小規模多機能自治という仕組みについて市はどのように捉えているか。 (4) 地域住民の議論の場をどのように設けるのか。市や各振興事務所はどのような役割を担うのか。 |
|
|
【午前11時40分から】 尾里集務 |
1.放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)について 放課後児童クラブは、放課後や学校の長期休暇中に、保護者が就労などにより家庭にいない小学生に対して学習や遊びの場所を提供し、その健全な育成を図る目的としていますが、下呂市としての成果と今後の取り組み状況は。 |
(1)放課後児童クラブの現状と課題は。 (2)放課後児童クラブに従事される方の支援員は、どのように確保しているか。 (3)放課後児童クラブに関する意思決定権と結果責任は福祉部こども家庭課が担っているが、子育ての関連から教育長の考えは。 |
|
2.緊急銃猟制度について 全国的にも問題になっている熊の市街地や建物に侵入といった事案が相次ぐ中、市町村の判断で特例的に猟銃の使用を可能とする事などを盛り込んだ改正鳥獣保護管理法が国会で可決・成立しました。今後市ではどのような対応を行っていくのか。 |
(1)9月1日から制度が始まるが、今後の予定は。また対応策は。
(2)制度の運用にあたり、猟友会との連携が重要になると思われますが、話し合いの進捗状況はいかがか。 |
|
|
【午後1時30分から】 今井政良 |
1.産後ケアの子育て支援について 子育て中の親にとって、安心して子どもを遊ばせる場所は本当に貴重ですが、曜日や時間が限られているため授乳やお昼寝で赤ちゃんのリズムが不規則なお母さんたちからは行きたくても時間を合わせるのが難しいという声が寄せられています。 市外から嫁いでこられた方や核家族では、頼れる人が少なく孤立しやすい現状があります。また、家族との価値観の違いから、孤立されるお母さんも多く見えます。 心身の負担が大きい産前産後の時期に助けが十分でないと産後うつなど孤立するお母さんを増やすだけでなく、現在妊娠中の方や、二人目・三人目の出産を考えている子育て中のお母さん方にとっても、大きなハードルとなっています。 |
(1)市の公民館を平日の日中住民が自由に使えるよう解放し、親子が安心して遊べる場所として活用していただいてはどうか。市の考えは。 (2)市の公民館等を活用した地域の子育て支援や健康増進活動がもっと気軽に行えるよう、使用料の見直しや減免制度を考えていただきたいが、市の考えは。 (3)産前産後に活用できる家事支援·食事支援体制の整備を市として前向きに考えていただきたいが、市の考えは。 |
|
2.小中学校の統合について 少子化に伴う児童生徒数の減少を見据えた統合について、少人数の学校区において温度差があります。 今まで小中学校の統合問題については、市主導でなく地元からの要望で対応されてきました。 |
(1)近年の出生数が百人前後の現状、市として今後どのように進められるのか。 (2)今後もその見解で進められるのか。 (3)公共施設の適正化の面からみてどうなのか。 |
|
|
3.避難所施設の整備計画について 近年の猛暑日対策の観点から、避難所施設としての空調施設整備を計画する必要があります。小中学校が最終避難所として各地域で指定されています。教育の観点からも、整備計画を策定する必要があります。 また、各地域の一時避難所である公民館等の空調設備の設置をコミュニティ補助金を活用し整備したいが、現状では半額補助であるため、自治会の負担が増え積極的な活用がなされていない。 公民館整備に対する補助率アップの考えはないか。 |
(1)避難所施設の整備計画について市としての考えは。 (2)コミュニティ補助金の補助率の見直しの考えは。 (3)公民館の空調設備の設置状況について。 |
※一般質問の発言予定時間は進行により変更することがあります。